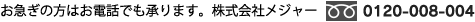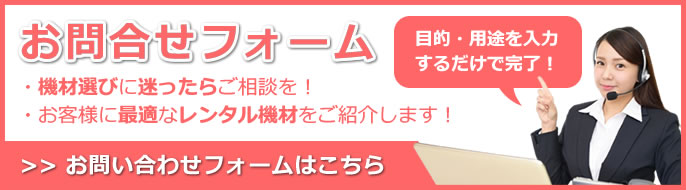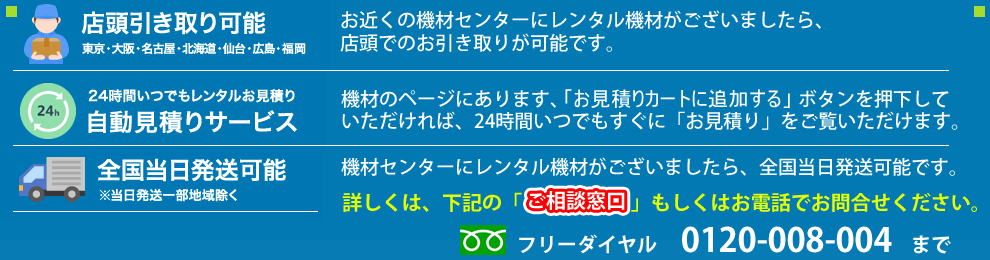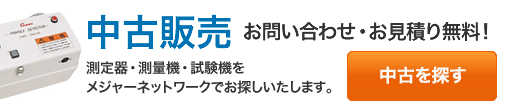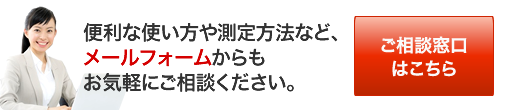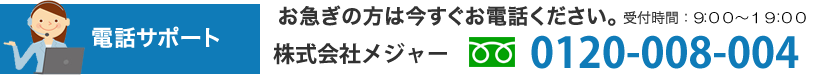多発する硫化水素による事故を防ぐには

なぜ硫化水素による事故が起こるのか。
硫化水素による点検作業事故は、毎年多数発生しており、その多くが死亡事故や重篤な障害につながっています。特に、下水道、マンホール、浄化槽、排水処理施設など、硫化水素が発生しやすい場所での作業中に事故が集中しています。
最近でも、2025/8/2に埼玉県行田市で下水管の点検中に1人の作業員がマンホール内に転落し、その後に入った作業員の計4人が死亡するという事故が発生しました。
当時、マンホール内に充満していたと考えられている有毒な硫化水素を吸って作業員がそのまま意識を失った可能性があると言われています。
事故発生のメカニズムと危険性
硫化水素は、空気より重い無色の気体で、腐った卵のような特徴的な臭いがします。しかし、高濃度になると嗅覚が麻痺してしまい、危険を察知できなくなるという非常に危険な特性を持っています。
- 急性中毒:
高濃度の硫化水素を吸入すると、数秒から数分で呼吸中枢が麻痺し、意識不明、呼吸停止、心停止に至ります。致死率が極めて高く、「即時失神性」の毒性があることで知られています。 - 二次災害の発生:
事故の最も大きな特徴は、倒れた作業員を助けようとした同僚や監視員が、適切な装備なしに現場に立ち入り、次々と中毒になってしまう二次災害が多発することです。これにより、被害が拡大し、複数の死亡者が出るケースも少なくありません。 - 作業環境の変化:
硫化水素は、汚泥の撹拌や化学反応によって急激に高濃度で発生することがあります。天候や気温、作業内容によって濃度が変動するため、作業前の測定だけでなく、作業中の継続的な監視が重要です。
主な事故事例と発生原因
以下に、過去に発生した硫化水素による作業事故の典型的なパターンと原因を挙げます。
- マンホール内での点検作業:
事例: マンホール内のはしごを降りている途中で作業員が意識を失い転落。助けに入った同僚も次々と倒れ、複数の死亡者が出た。
原因: 作業前に硫化水素濃度の測定を怠った、または測定したが作業中に濃度が急上昇した。換気が不十分であった。救助者が適切な呼吸用保護具を着用せずに救助に入った。 - 浄化槽や排水処理施設の清掃・点検:
事例: 浄化槽の清掃作業中に、硫化水素中毒により作業員が倒れた。
原因: 有害ガスの存在を軽視し、換気やガス濃度の測定をせずに作業を開始した。 - 温泉施設や温泉源泉の管理:
事例: 温泉源泉の管理作業中、硫化水素がたまりやすい雪の窪地で、火山ガスを吸入し、複数の人が倒れて死亡した。
原因: 硫化水素が高濃度で滞留しやすい場所であるにもかかわらず、危険性の認識が低く、保護具なしで立ち入った。
事故を防止するための対策
これらの事故を防止するためには、以下の対策を徹底することが不可欠です。
- 危険場所の明確な認識と事前対策:
硫化水素や酸欠の危険がある場所(下水道、マンホール、浄化槽、タンク、温泉施設など)を特定し、関係者全員に周知する。
立ち入り禁止の看板を設置する。 - 作業環境の厳格な管理:
ガス濃度の測定: 作業開始前、休憩後、および作業中は定期的に、ガス検知器を用いて酸素濃度と硫化水素濃度を測定する。
換気の徹底: 送風機などを使って継続的に換気を行い、酸素濃度18%以上、硫化水素濃度10ppm以下の安全基準を確保する。 - 保護具の使用と非常時の備え:
換気が不十分な場合や、安全基準を満たせない場合は、送気マスクや空気呼吸器を必ず着用する。
救助用の呼吸器やはしご、ロープなどの非常用設備を準備し、使用方法を訓練する。 - 安全衛生教育と作業体制の確立:
硫化水素の危険性、中毒症状、正しい作業手順、非常時の対応などについて、作業員全員に教育を徹底する。
酸素欠乏危険作業主任者を選任し、指揮・監督を行わせる。
複数の作業員で作業を行い、必ず監視人を配置する。監視人は、異常発生時に直ちに救助要請や通報を行う役割を担う。 - 救助の原則:
倒れている人を発見しても、決して無防備に近づかない。
救助者は、必ず適切な呼吸用保護具を着用し、二次災害を防ぐ。
速やかに119番に通報し、専門の救助隊に救出を依頼する。
マンホールや管内での作業事故の防止に役立つ測定器
主な測定機器は以下になります。
- 装着型(個人用)ガス検知器: 「ポータブルガスモニター(CH4/O2/H2S/CO/SO2) GX-3R Pro」など。
- 吸引式ガス検知器: 「ポータブルマルチガスモニター GX-6000(ガス5種類)」など。
まとめ
硫化水素による事故は、適切な知識と対策があれば防ぐことが可能です。安易な判断や「大丈夫だろう」という油断が、命取りになることを常に認識することが重要です。